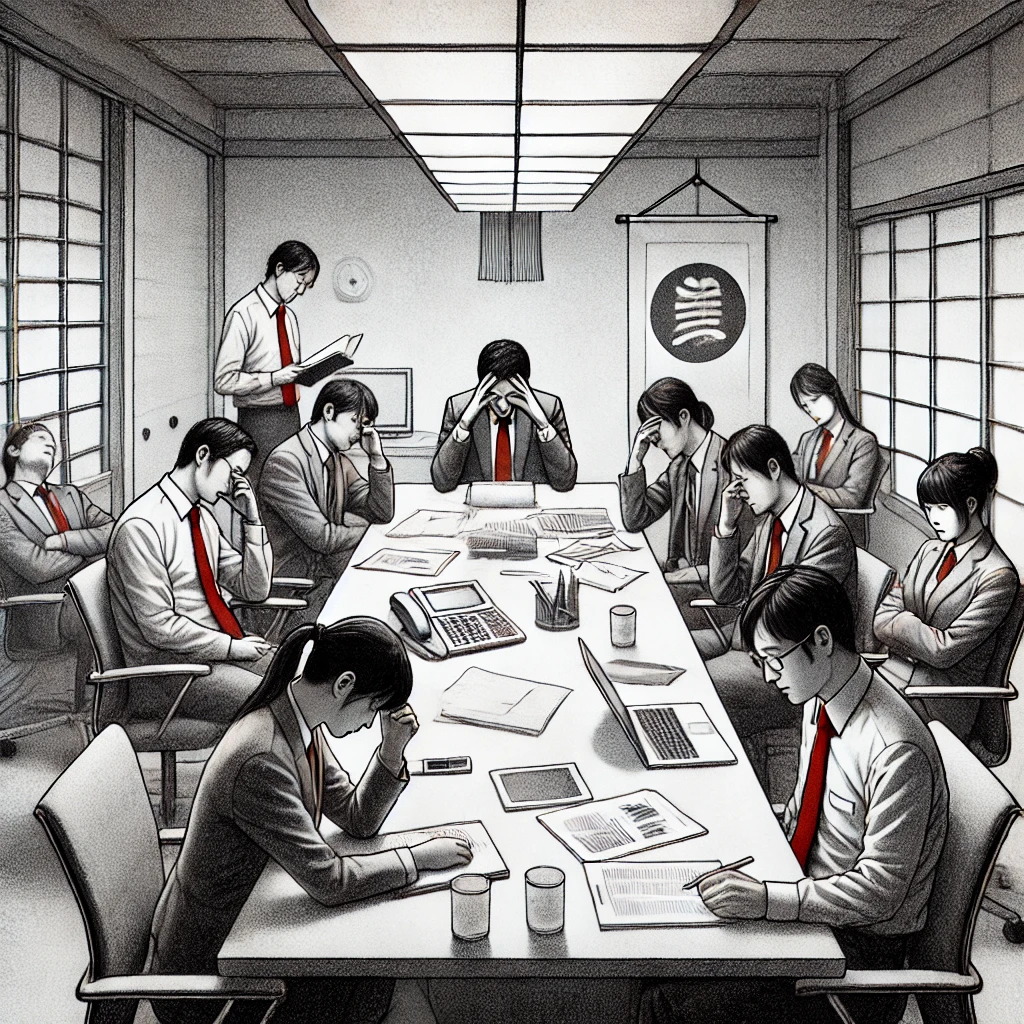時計を見ると、もう2時間が経過。
みんな疲れ切った顔で、スマホをいじったり、資料をペラペラめくったりしている。
「で、結局、どうするんでしたっけ?」
誰かのぼやきが聞こえた瞬間、会議室の空気が凍りつく。
長い時間を費やしたのに、結論はゼロ。ため息とともに散会する。
「この会議、本当に必要だったのか?」
そんな疑問を抱いたことは、あなたにもあるはずです。
特に40代・50代の働く大人にとって、時間は最も貴重なリソース。
にもかかわらず、多くの企業では「決まらない会議」が常態化している。
なぜ、会議は「何も決まらない場」になってしまうのでしょうか?
どうすれば、実のある会議にできるのか?
この記事では、ムダな会議が生まれる原因と、それを根本的に解決する方法を解説します。
これを読めばわかること
✅ 会議が目的化してしまう原因とは?
✅ ムダな会議を減らすための具体的な方法
✅ 決まる会議を実現するためのアクションプラン
「話し合い」ではなく「会議をすること」が目的になっている
会議が終わったあと、「結局、何も決まらなかったな」と感じたことはありませんか?
それは、会議の目的が「意思決定」ではなく、「会議をすること自体」になってしまっているからです。
では、なぜそんなことが起こるのか?
理由は大きく3つ考えられます。
「決まらない会議」が生まれる3つの原因
1. アジェンダ(議題)が曖昧
「とりあえず集まって話しましょう」という会議は、何を決めるべきなのかが不明確。
参加者も「とりあえず聞いておけばいいか」となり、意見が出にくくなる。
👉 解決策:事前に「会議のゴール」を明確に設定する
- 「A案とB案のどちらを採用するか決める」
- 「来月のプロジェクトの優先順位を決定する」
など、具体的な目標を定めるだけで、会議の進行は劇的に変わります。
2. 決定権者がいない
「持ち帰って確認します」と言われた瞬間、その会議は無意味になる。
決定権のないメンバーだけが集まる会議では、何も決まらないことばかり。
👉 解決策:決定権者を必ず会議に参加させる
- どうしても出席できないなら、事前にメールやチャットで意見をもらい、最終判断を仰ぐ仕組みを作りましょう。
3. 議論が発散しすぎて収束しない
最初は一つの課題について話していたのに、「そういえばこの件も…」と話題が広がりすぎて、
最終的に何を決めるべきだったのか、全員が見失ってしまいます。
👉 解決策:議題ごとに時間を設定し、タイムキーパーを設ける
- 「この議題は10分」「この決定には15分」と時間を区切る
- 進行役が話をまとめ、論点を整理しながら進める
【解決策】決まる会議に変えるための4つのルール
ムダな会議をなくし、「決まる会議」に変えるためのシンプルなルールを紹介します。
✅ 1. 事前に「この会議のゴールは何か?」を明確にする
→ 何を決めるための会議なのか、事前に全員に共有する。
✅ 2. 決定権のある人を必ず入れる
→ いないなら、事前に意見をもらい、最終判断を仰ぐ仕組みを作る。
✅ 3. 議論の枠を決め、議題ごとに時間配分をする
→ 「この議題は10分」「この決定には15分」など、時間を区切る。
✅ 4. 会議の最後に「誰が」「何をするか」を明確にする
→ 「次回までに各自考えておきましょう」はNG。
→ 「AさんがBの資料を作る」「CさんがD社と交渉する」など、具体的なアクションを決める。
「そもそも会議を減らす」ことも重要
本当に、その会議は必要なのか?
「集まる必要がないなら、メールやチャットで済ませる」という選択肢もある。
具体的な方法
✅ 進捗報告はチャットで共有する
✅ 重要な決定だけを短時間のミーティングで行う
✅ 定例会議を廃止し、必要なときだけ開催する
こうすることで、無駄な会議を減らし、時間をより生産的に使うことができます。
まとめ:ムダな会議から抜け出すために
✔ 会議が目的化すると、何も決まらないまま時間だけが過ぎる
✔ 「何を決めるための会議か?」を明確にし、決定権のある人を参加させる
✔ 議題ごとに時間を区切り、最後に具体的なアクションを決める
✔ そもそも会議が本当に必要かを見直し、可能なら削減する
【今すぐできる3つのアクション】
1️⃣ 次の会議のアジェンダを具体的に作成する
2️⃣ 参加者を見直し、決定権のある人がいるか確認する
3️⃣ 「この会議、本当に必要?」と自問し、メールやチャットで代替できるか検討する
これを試せば、「この時間で何か決まった?」というモヤモヤから解放されるはずです。